【Spotlight 企業進出】新電池工場日産再建で一抹の不安/カーアイランドの先駆者「日産」の九州進出は曲折たどる
2025年03月20日
ホンダとの経営統合が破談になった日産自動車の今後の経営再建問題は、子会社の日産自動車九州のある福岡県苅田町よりも、約1500億円を投じるEV電池工場の舞台となる北九州市の方が不安感を募らせている。EV関連産業の集積も高まるなか、日産の再建次第という状況は地域戦略に暗い影を落としかねない事態となっている。
九州はリストラの対象外に 北九州市内に初の工場進出
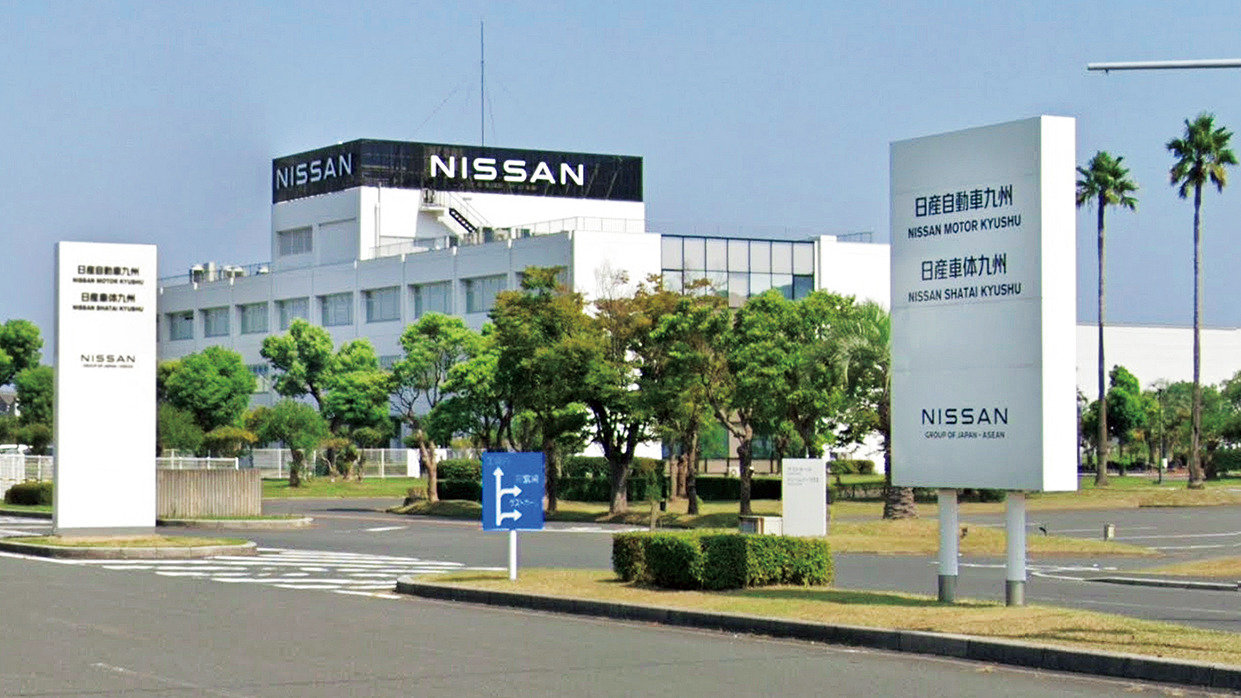
日産は経営再建に向けて、タイなどの3工場を2026年度までに閉鎖し生産能力を削減、併せて9000人もの人員削減を行う大ナタを振るう計画を立てている。苅田町にある日産自動車九州と日産車体九州での生産台数が合計50万台を超え、国内生産の7割を担うこともあり、九州の生産拠点はそうしたリストラの対象からは外れているためか、地場サプライヤーも含めて、大きな動揺はなかった。実際、日産の役員と面会する機会があった北九州の地元経済人は「九州は今回の人員削減の中に一人も入れていないと言っていた」と明かしている。
そんななか、ホンダとの経営統合が破断になる前に発表されたのが、北九州市若松区に建設するEV向け電池工場の建設だった。響灘エリアに約15万平方メートルの土地を取得、1533億円を投じて工場を建設するというもの。26年度中に着工し、28年度の稼働開始を目指している。県と北九州市がそれぞれ最大50億円を補助する予定。具体的には、次世代軽EV用の「リン酸鉄リチウムイオン電池(LFP電池)」を製造するもので、レアメタルを使用せず、安価で安定性が高いのが特徴だ。誘致には北九州市と福岡県が連携して取り組み、実現にこぎつけた。今回は日産が北九州市に造る初めての工場となる。同市にとって過去最大の投資額であり、工場では約500人の新規雇用の創出も予定され、過去10年で最多となる。企業誘致を重要施策の一つとして掲げる武内和久北九州市長にとっても、就任後では最大のプロジェクト進出となる。
素材型産業からの転換が急務 「銀座商会N作戦」で誘致成功
日産の前身は明治時代に北九州市に設立された「戸畑鋳物」で、九州で最初に自動車生産を開始したのが日産の九州工場だ。今年は1975年の操業から50年目の節目に当たる。その後に、トヨタ自動車九州(92年)やダイハツ九州(2004年)が進出し、カーアイランド九州の礎を築いた。
実は、日産の九州進出をめぐって裏側では激烈な駆け引きが展開されていたことを知る人は少ない。当時の九州経済はエネルギー革命で石炭産業が斜陽となり重厚長大型の素材産業に依存していたことで、急激な落ち込みに見舞われていた。そこで加工型産業への転換を図るために誘致が検討されたのが自動車産業だった。誘致には当時の九州・山口経済連合会などの地元経済界が熱心に働きかけを行っていた一方で、福岡県も当時の亀井光知事が先頭に立ち、誘致活動を展開していた。1970年に東京商工会議所主催の経済視察団が筑豊、苅田など県内の産炭地域を訪れた際、メンバーにいた日産幹部から「生産即輸出できるような臨海部の新工場建設を計画している」との話が福岡県関係者にもたらされる。
むろんこうした日産の意向はすぐに全国に漏れてしまい、自治体で激烈な誘致合戦の発展した。そこで福岡県が秘密裏に繰り広げた戦略が「銀座商会N作戦」。当時、日産は東京・銀座に本社を構えていて、それを福岡県は「銀座商会」という暗号で呼び、ひそかに「N」、いわゆる日産の誘致を意味するものであった。最後まで大分県豊後高田市と競い合ったが、福岡県の交渉が実を結び、福岡県苅田町へ進出が決定する。
ところが、73年に調印式を終えたものの、着工に至るまでに紆余曲折があった。いわゆるオイルショックの影響だ。自動車産業はその製造のために石油を多く使用する。そのため総需要抑制に乗り出した当時の通産省は「こんな時勢に新工場建設はもってのほか」と、日産側に圧力を強めた。そのため着工は延び延びとなり、苦悩した福岡県と日産だったがここで日産が一計を案じ「新型エンジンの開発工場」という名目を立てた。総需要抑制のなかでも排ガス抑制のエンジン開発ということならば、国も文句は言わないだろうとの判断であった。結果的にはこの機転が功を奏し、無事に着工。75年に稼働を開始した。
トヨタも苅田に蓄電池工場 関連産業集積で商機期待も
同市内には100社以上の自動車関連企業などが集積していることに加え、新工場が進出すれば、さらにEV関連産業が集積する。トヨタ自動車は苅田町の新松山臨海工業団地に次世代蓄電池の工場を新設し、28年に生産を開始する計画。また、トヨタ自動車は2035年までに高級車ブランド「レクサス」をEV化する計画で、トヨタ九州がその生産拠点を担うとみられている。また、EVモーターズ・ジャパン(北九州市)は国内初となる商用EV専用工場を完成させ、今春から大型EVバスの組み立てを開始する。
もっとも、この電池工場が無事に建設されるのかどうか、日産の再建次第という点が不安材料となっている。これはあくまで日産単独の事業であるため、ホンダとの破談は直接的には影響しないとみられている。だが、日産の内田社長自身も「単独で生き残っていくことは厳しい」と認めているように、日産本体の再建にはホンダに代わるパートナー探しが鍵を握る。台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業(ホンハイ)の名前も取りざたされている。仮にホンダとの経営統合がうまく進んでいれば、今回の新電池工場は、国内におけるEV開発・製造のシンボリックな存在となったはずだ。現状ではEV開発でホンダとの協業は継続するとされているが、「統合破断でもEV協業ができるのか」との懐疑的な見方は少なくない。
日産が業績回復を図ることができなければ、新電池工場だけでなく、九州の生産拠点へ悪影響が及ぶ可能性がないわけではない。別の地元経済人は「北部九州には、モーターに関わる企業がたくさんある。こうした企業を後押しするためにも新工場は前に進めるべきだ」と話し、期待感を示しているが、「(進出には)正直なところ一抹の不安も残る」として、日産の今後の動きを注視していくようだ。
(鳥海 和史)


